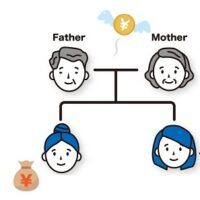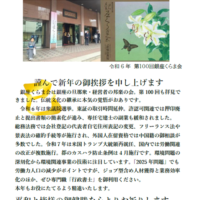相続による債務承継
本日は相続による義務、債務の承継、特に承継割合についてのコラムです。
現時点での改正民法施行は令和6年5月24日施行が直近の施行日でした。
本日のコラムは令和7年2月現在の施行法を基にしています。

相続財産にプラスの財産もマイナスの財産(=債務)も含まれることは御存知のとおりです。
その際に選択する相続の種類(単純承認/限定承認/相続放棄)と手続きについて今回は書きませんが、以前のコラムも御参照下さい。
「債務・義務」は金銭に限定されませんが、元の性質が金銭でなくとも最終的に損害賠償や代償金として金銭に形を変えることが一般的です。
■義務承継の割合はどうなるか
【参考条文】民法第899条・902条・902条の2
遺言者は、遺言により複数いる相続人の相続分の指定をすることができ、相続人はその割合に応じて権利義務を承継します。
※特定財産承継遺言との違いに御留意ください
しかし、遺言者の意思で指定した承継割合について債権者にも従わせる、というのは理にかないません。
そのため民法第902条の2で債権者は共同相続人に対して『法定相続分』を請求することができる、と明文化されました。
債権者の立場としては債権の回収が可能な相続人(十分な資金を保有しているなど)に請求することが現実的です。
![]() 相続人の立場:
相続人の立場:
遺言で自分とは別の相続人が債務を承継すると指定されていても、債権者の承認を得られるとは限らず、早めに確認するようになさって下さい。
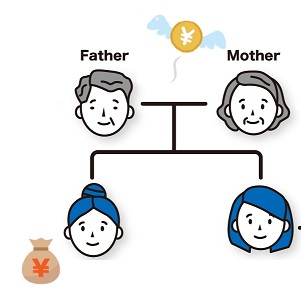
![]() 債権者の立場:
債権者の立場:
・いったん、遺言で指定された相続分に基づいた請求をしたときは、指定相続分による債務承継に応じたことになりますので、権利行使の前に慎重に判断しましょう。
・指定相続分に応じるかの判断時期に制限はありませんが、債権そのものの時効には注意して下さい。
■遺産分割協議での留意点
遺言による相続分の指定ではなく、相続が発生した後(=被相続人の死亡後)に相続人の間で遺産分割協議をおこなう際でも同様です。
相続人だけの間で、誰が相続債務/義務を引き受けるかと合意しただけでは、あくまで相続人間での効力にとどまります。
【参考条文】民法第472条(免責的債務引受の要件及び効果)
ひとことに“相続”と言っても、包括的に相続人としての地位なのか、
遺産を包括的な割合で相続する(させる)のか、
特定の財産や義務を相続する(させる)のか etc. 人により考え方はさまざまです。
検討は専門家に御相談ください。
お問い合わせはフォームからどうぞ。